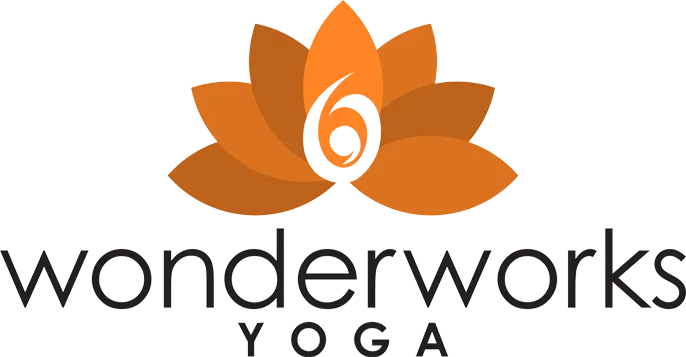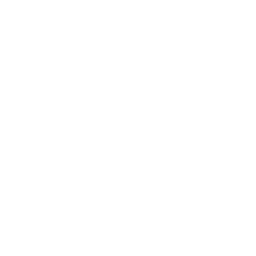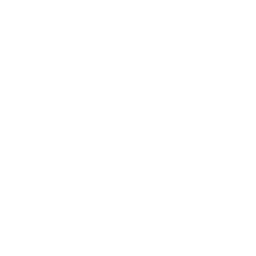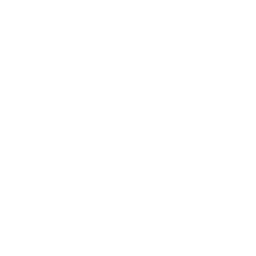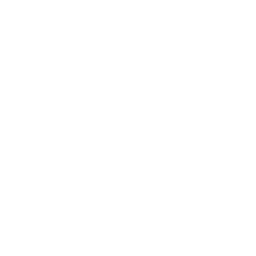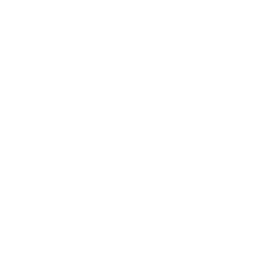前編:白髪は防げる!減らせる!若々しい髪を育むライフスタイル(東洋医学編)

今日は、髪の老化を防ぐ方法について、東洋医学、科学的な視点、そして私自身の経験からお話しします。
白髪が目立たないツヤとボリュームのある髪は若さの象徴ともいえます。私はアラフィフですが、髪は染めておらず(昔のハイライトが下の方に少し残っています)、髪の長さは腰まであります(自己最長かも😆)。枝毛もほとんどなく、ツヤとボリュームも維持できています。
「白髪は遺伝で決まる」と思われがちですが、エピジェネティクスという考え方では、遺伝的な要素があってもライフスタイルによって体質や老化スピードは変わります。
エピジェネティクスと遺伝の関係
エピジェネティクス(epigenetics)とは?
DNAの「設計図」自体は変わらないけれど、その遺伝子が働くかどうかは生活環境(食事・睡眠・運動・ストレス・毒素など)で変化する、という考え方です。
例えば…
- 抗酸化物質の多い食事で、老化関連遺伝子の働きを抑える
- 運動習慣によってテロメアが伸びる(老化のスピードダウン)
- 運動習慣で癌リスクが下がる
これらのように、後天的な調整を通して遺伝子の働き方が変わることを「エピジェネティックな変化」といいます。
髪の健康を守る東洋医学の視点
東洋医学では、髪は「血の余り」とされ、血行が重要と考えられます。頭皮への血流を促すために運動をしたり、マッサージを行うのはとても効果的です。
実際、私の生徒さんの中にも、毎日後頭部の筋膜リリースを習慣にしたところ「血行が良くなって白髪が減った」と報告してくれた方がいます。
さらに老化と深く関わる臓器は「腎」とされ、腎には先天的な生命エネルギー「精(せい)」が蓄えられています。過度なストレスや疲労の多い生活を送ると、この精が消耗し老化が加速します。
腎を労わるためには、リラックス・瞑想・深い呼吸・十分な休息や睡眠が不可欠です。
食事面では、腎を養う黒い食材(黒胡麻、黒豆、黒米、黒きくらげ)や海藻類が有効です。私の母も「海藻を食べると美しい髪になるよ」とよく言っていましたが、私は子どもの頃から海藻が大好きでした。
前編のまとめ
遺伝や年齢に関わらず、ライフスタイルの工夫で髪の老化スピードは変わります。
次回の後編では、科学的な視点から白髪と酵素の関係、そして私が実践している8つの習慣について詳しくお話しします!